◆以下のメモは新しい歴史教科書をつくる会『史』11月号にもとづく
①1970年間まで
歴史学界やメディアは「日本が悪かった」という物語を流布し続けたが、文科省はそれに抵抗していた。
「これだけを守っていけば、何とか国家は維持できる」という歴史教科書を守ろうとしてきた。
②1970年「家永教科書訴訟の杉本判決」
検定制度は合憲だとしたが、いくつかの検定意見(文科省が教科書につけた意見)について、思想の自由・表現の自由を侵す可能性があるとした。日教組や左翼はこれを勝利判決だと宣伝し、以後杉本判決は左翼の教科書づくりの旗印になった。
③1970年代「日中国交回復と南京事件」
本田勝一『中国の旅』(朝日新聞)をきっかけに、南京事件が高校教科書にはじめて載り、中学校の教科書に載り、小学校の教科書にまで載るようになった。中国よりも先に日本の歴史教科書が書きはじめ文科所検定を通ってしまった。
④1982年「侵略進出誤報事件」
教科書検定で文部省が日本の「侵略」の記述を、「進出」に書き換えさせたと新聞各紙が一斉に報道したが、フェイクだったとわかる。しかし、それを奇貨として中国共産党が人民日報に「日本は過去の侵略を教科書検定で隠蔽している」という批判記事を連日掲載した。メディアは、これが誤報だということを明らかにすることをしなかった。
これが、日本の教科書に外国が口を出した最初の事件になった。
屈服した宮澤喜一官房長官は謝罪声明を出し、「近隣諸国条項」を教科書検定基準につけ加え、現在もそれが残っている。
「日本を守る国民会議」(日本会議の前身)は高校教科書『新編日本史』を出しいったんは合格した。しかし、朝日新聞がキャンペーンを張って、政府は4次にわたる超法規的な検定が行われてしまった。
ここで、歴史教科書検定は決定的な逆コースに入った。文部省が保守的な記述を否定する役目を果たすようになったのである。
小学校の意教科書にまで、毒々しい反日写真や中国共産党の抗日壁画やでっち上げの資料などが掲載されるようになっっていった。
⑤1996年「中学校の歴史教科書に一斉に従軍慰安婦の記述が載った」
新しい歴史教科書をつくる会が結成された。翌97年には「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」が結成された。中川昭一会長、安倍晋三事務局長
⑥2000年代「つくる会効果」
2001年に新しい歴史教科書をつくる会の教科書(育鵬社版)が検定に合格し話題になった。が、1回目の採択で「下都賀事件」などの暴力的な反対運動があり、その結果採択はふるわなかった。
つくる会は教科書採択の権限は教育委員会にあると広報したため、それまでは組合の教師などに丸投げしていた教科書採択に教育委員会が参加するようになった。このため、教科書会社は上記のような日本の悪を糾弾する毒々しい写真や資料を掲載できなくなっていった。従軍慰安婦の記述もほぼなくなった。
(以下略)


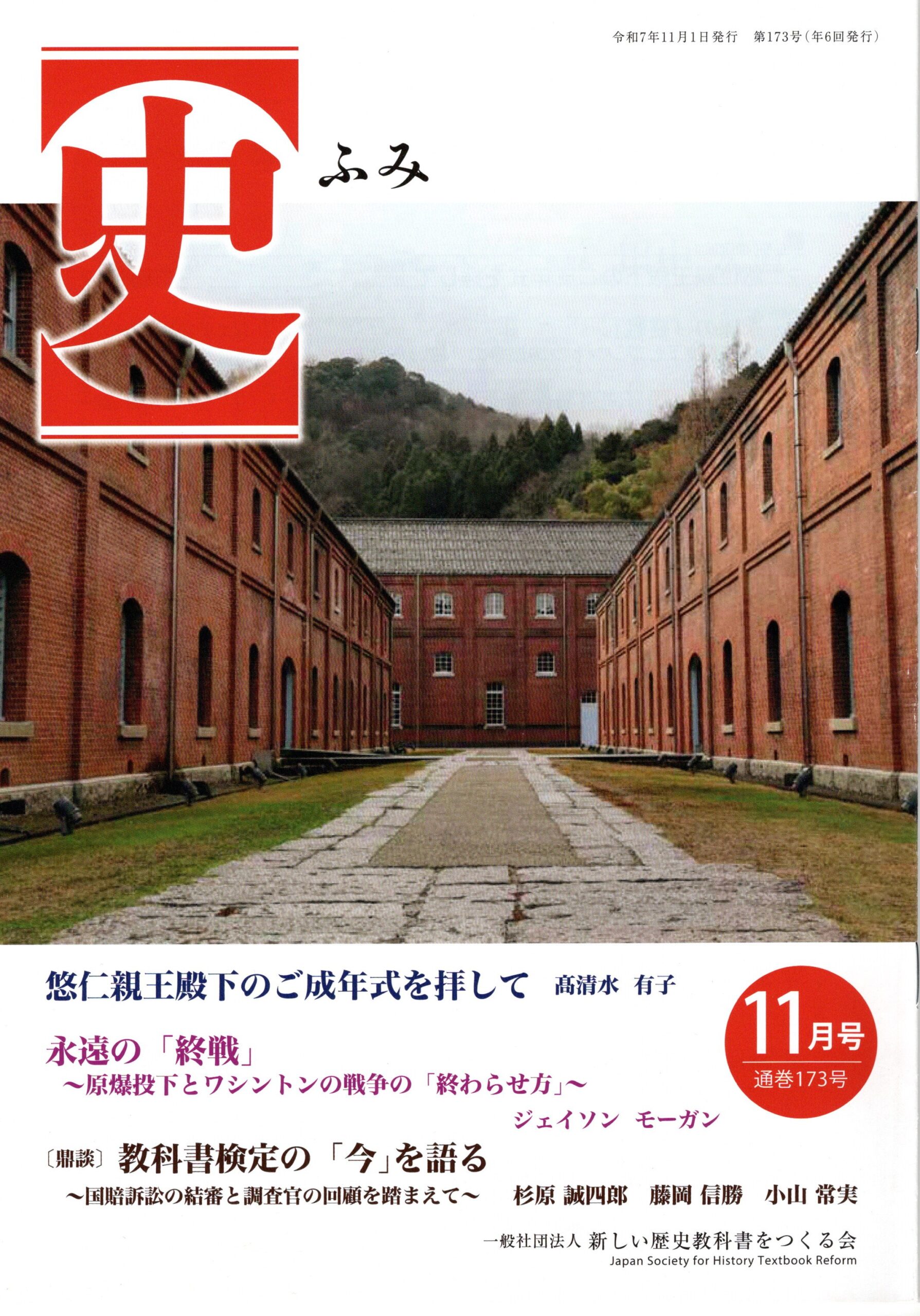




コメント