古墳時代
「古墳時代」で大和朝廷(王権)による日本統一を教えます。
むかしは「大和時代」でしたが古事記・日本書紀の歴史は教えないのが戦後教育の縛りになっているので、考古学名称である「古墳時代」が採用されています。「大和時代」のほうが時代の本質が伝わりますね。
教科書には伝仁徳天皇量の写真が大きく載っています。世界一大きい大王の墓です。歴史を教えていると「世界一」や「世界初」が結構出てきます。まあほかの国でもあるでしょうが子供たちはこういうオリジナリティをとても喜びます。
「古墳時代」ですから前方後円墳や考古学的な発見を教えて終わりという授業が多いが、だいじなのは
「神武天皇が建国した国が、血筋をひく大王たちによって大きく発展し、大和朝廷となって日本を統一した」
という史実を学ぶことです。これが今に続く「日本」の始まりになりました。
教科書には出てきませんが、崇神天皇から雄略天皇の時代のことだと教えてもいいでしょう。崇神の磯城瑞籬宮(しきみずがきのみや)は奈良県桜井市金屋(纏向遺跡)に、雄略の泊瀬朝倉宮(はつせあさくらのみや)は同市の黒崎(脇本遺跡)にあったと考えられます。
3世紀後半から5世紀なかばくらいまでおよそ200年間の大和朝廷の偉大な業績です。
授業では「日本統一」を以下で実証します。
①前方後円墳が奈良盆地で始まる。
②超巨大な前方後円墳は奈良と大阪にある。
③前方後円墳(および同じ副葬品など)が全国に分布する。
④宋書に出てくる雄略天皇の書簡。
⑤埼玉県と長崎県出土の剣の銘文(ワカタケル)など。考古学が日本書紀とつながります。
(おまけ)教科書は長い間共産主義の階級闘争史観に汚染されてきたので、仁徳天皇陵を教えるときに必ず大古墳をつくるのがいかに大変で無駄なことだったかを教えようとしました。想像図には鞭をふるって人民を働かせる支配者と苦しみにあえぎながら働かされる人民が描かれていました。被支配者に共感させ支配者への憎悪を育てる歴史教育です。もちろんそういう見方も可能ですがそれだけでは一面的に過ぎます。巨大な古墳を造営する場面で「問題」を設定してみると、子供たちは「偉大なリーダーへの感謝の気持ちでつくったのでは?」といった教科書とが異なった視点を出してくるようになります。埴輪に見られる人物たちの表情などが証拠になります。この階級闘争史観を相対化する授業づくりは、律令制の租庸調とか、江戸時代の貧農史観とか、百姓一揆とか、教科書のあちこちで出てくるので、けっこう試されたとい思います。これはシン皇国史観とは話が別ですけれど。
建国神話の授業
神話の授業をなぜここに置くか?については前に少し説明しましたので参照してください。
イザナキ・イザナミの国生み、神生み。三貴神、アマテラスオオミカミの天の岩戸、スサノオノミコトの八岐大蛇、オオクニヌシノミコトの因幡の白兎、出雲の国譲り、ニニギノミコトの天孫降臨、国つ神との婚姻、カムヤマトイワレヒコノミコトの東征、初代神武天皇に即位までをざっと教える。不十分だが。
日本には神様がたくさんいて、日本人は自然のすべてとご先祖様を敬い感謝してきたこと。
日本の神様は成長すること。
日本の神様は神社に祀られていること。
アマテラスオオミカミは皇祖神だと考えられていること。
国譲り神話は世界でも珍しい日本独自の物語であること。
日本の神様は大勢いるから大事なことはみんなで話し合っていたこと。
天上(高天原)の神々と地上(山と海など)の神々の協力で日本が生まれてくること。
天壌無窮の神勅と即位建都の詔。
などを重要な内容として伝えたい。
ただ、いまのところ建国神話の授業は不十分であり、学問と知恵を集めて「日本人の基礎教養としての神話を子供たちにどう伝えていく」かという視点で研究してほしいと考えている。
歴史だけで教えるにはカリキュラム上制限があり、あまり十分な時間をかけられない。小学校の低学年から中学校修了まで(義務教育のなかで)、自国の建国神話をしっかり教えるための望ましい場&時間(国語・道徳・総合など)と望ましいカリキュラムがほしい。
以前、白駒妃登美さんが新教科「日本(文化)」が必要だと提案されていたが実におっしゃる通り。日本人になるための基礎教養を義務教育で十分に教えられない現状は情けないとしか言いようがありません。
国際化社会だから1年生から英語を教えようとがんばっているが本末転倒です。国際化社会だからこそ「日本」を教えなくてはいけないんじゃないでしょうか。
またいろいろ脱線していますが、こんな感じで続けていきます。
(つづく)









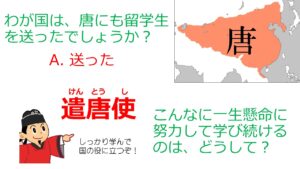
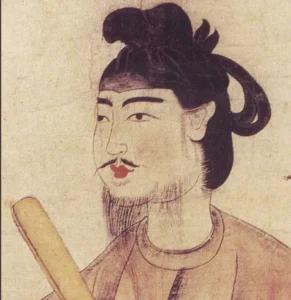
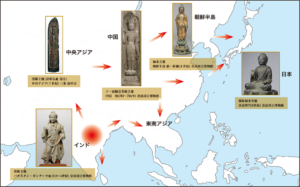
コメント